BLOG
【SEO対策】SEOで評価される“被リンク”とは?検索順位に効く外部からの評価
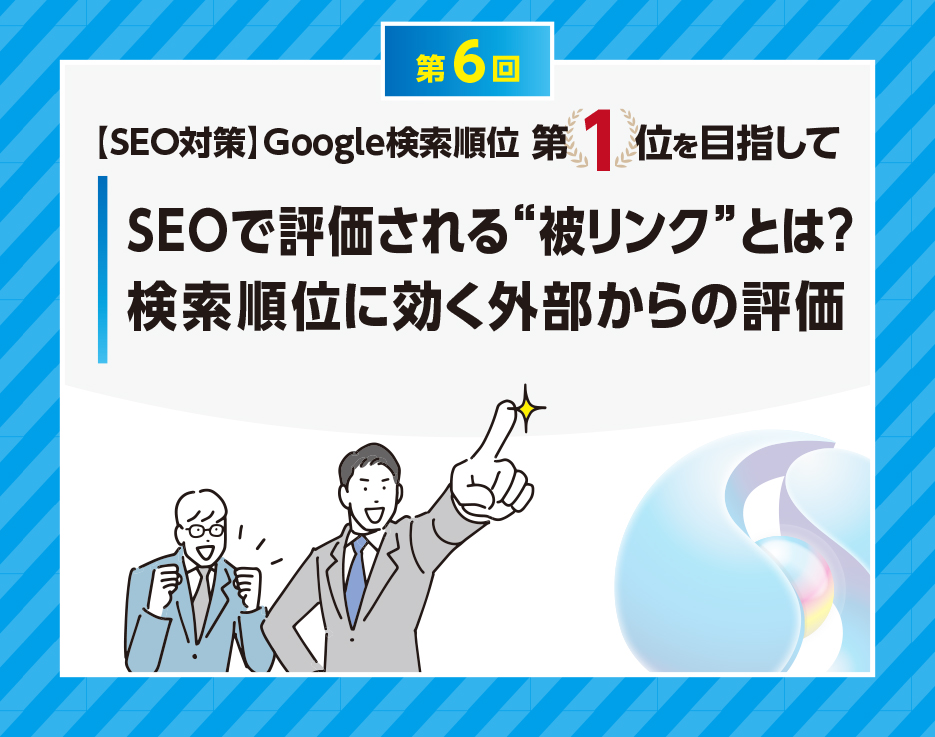
こんにちは!サンコー印刷です。
現在弊社では、自社のホームページが「岡山 ホームページ制作」で検索順位1位に表示されるように、SEO対策に取り組み、その記録をブログとして残していく取り組みを行っています。
▶プロローグ
▶第1回【SEO対策】タイトルタグとメタディスクリプションの見直し
▶第2回【SEO対策】Googleビジネスプロフィール(旧Googleマイビジネス)の見直し
▶第3回【SEO対策】alt属性を活用したSEO対策
▶第4回【SEO対策】PageSpeed Insightsとは?【ツール紹介】
▶第5回【SEO対策】Googleサーチコンソールとは?【ツール紹介】
第6回目となる今回は、
SEO対策を語るうえで、欠かせないキーワードのひとつである「被リンク」についてまとめました。
被リンクは、検索エンジンがページの信頼性や価値を判断する際の材料となるもので、検索順位に与える影響も大きいとされています。
被リンクとは?
被リンク(バックリンク)とは、他のWebサイトから自分のサイトへ向けて貼られたリンクのことを指します。
例)他のブログで「おすすめのホームページ制作会社」として、自社のサイトURLが紹介された場合、そのリンクが「被リンク」となります。
これは、インターネット上での「推薦」や「信頼の証」のようなものであり、Googleをはじめとする検索エンジンは、被リンクの量と質を検索順位の評価指標として重視しています。
なぜ被リンクはSEOに効果があるのか?
■ Googleの評価アルゴリズムに組み込まれている
Googleでは、信頼できるサイトから多くリンクされているページは価値が高いとみなされます。
この考え方のベースとなっているのが、Google創業当時に導入された 「PageRank(ページランク)」 という仕組みです。
PageRankとは?
ページがどれだけ多く、どれだけ信頼性のあるリンクを受けているかによって、その重要性を評価する仕組み。
■ 自然な被リンクは「第三者からの信頼」
自社でどれだけ「良いサイトです!」とアピールしても、第三者の推薦がなければGoogleの評価にはつながりにくいもの。
自然に発生した被リンクは、検索エンジンにとって信頼性の裏付けになります。
SEOに強い「良い被リンク」の特徴
以下のようなリンクは、Googleから高く評価されやすいです。
| 特 徴 | 内 容 |
|---|---|
| 関連性がある | 同じ業界・テーマのサイトからのリンク(例:デザイン系ブログ → 制作会社) |
| 権威性がある | 公的機関・大学・大手ニュースサイトなど |
| 自然に貼られている | 金銭やリンク交換ではなく、純粋な紹介として貼られている |
| 適切なアンカーテキスト | 「詳しくはこちら」ではなく、具体的な内容を含むテキスト(例:「岡山のWEB制作会社」など) |
マイナス評価になる「悪い被リンク」の例
Googleは、不自然または悪質な被リンクについてはスパム行為として判断し、検索順位に悪影響を与えることがあります。
以下のようなリンクは要注意です。
✔ 被リンクを大量販売している業者からのリンク
✔ 中身のないリンク集・低品質なディレクトリサイト
✔ 無関係なジャンル(例:海外カジノ → 教育系ブログ)
✔ 自作自演の大量な相互リンクネットワーク
被リンクを増やすには?効果的な3つの方法
① 良質なコンテンツを作成・発信する
- 役立つ情報(チェックリスト・テンプレート・事例など)を提供
- 特定のテーマに特化したノウハウや地域情報(例:岡山のWEB制作動向)を継続的に発信
② 業界団体やポータルサイトに登録する
- 自社ホームページへのリンク掲載が可能な信頼性の高い団体や地域系ポータルを活用
③ プレスリリースやニュースメディアを活用する
- 新サービス・キャンペーンなどをメディアに紹介してもらい、自然なリンクを得る
被リンク対策の注意点
- 質>量:たくさんリンクを集めるより、信頼性の高いサイトから1本の方が効果的です。
- Googleのガイドラインに沿って行うこと:購入・交換による被リンク施策はペナルティ対象になる可能性があります。
- 定期的にリンク元を確認する:Google Search ConsoleやSEOツールを使って、不審なリンクがないかチェックしておきましょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
被リンクは、SEOにおける「外部からの評価」を表す重要な要素です。
特に、自然に・信頼できるサイトから獲得したリンクは、検索順位の上昇に大きく貢献します。
まずは、紹介したくなるような良質なコンテンツを作ることが何よりの近道。
そして、地道な情報発信や関係性づくりが、被リンク獲得の土台となります。
今後も引き続き、実践した内容や得られた学びを記録していきますので、ぜひ参考にしてみてください!
サンコー印刷では情報発信の様々なノウハウを活かし「伝わる」ホームページ制作を承っています。

