BLOG
句読点NG!?知っておきたい挨拶状の基本ルール
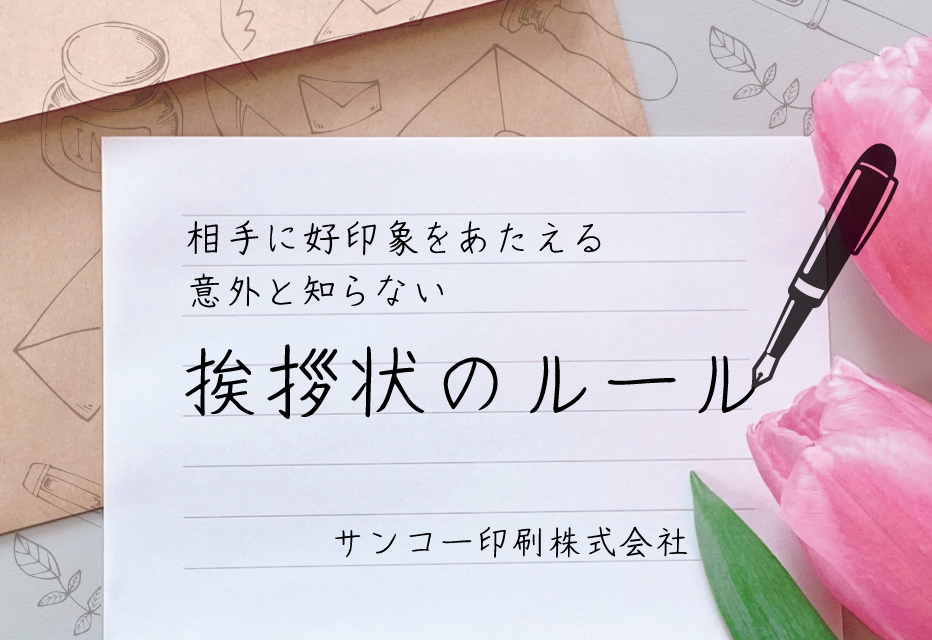
こんにちは!営業部インサイドセールスチームです。
2月は、新年度の商談や人事異動の準備が進む時期。
改めて「挨拶状」を送る機会が増える方も多いのではないでしょうか?
そんなとき、ちょっとしたマナーを押さえておくだけで、
よりスマートな印象を与えられます。
今回は、挨拶状の基本ルールと、
意外と知らない豆知識をご紹介します!
挨拶状の基本
挨拶状には決まった構成があることをご存じでしょうか?
一般的には、以下の流れで書くのが正式とされています。
「頭語」→「時候の挨拶」→「本文」→「結びの挨拶」→「結語」→「日付」→「差出人」
この形式は、公式な挨拶状だけでなく、はがきや絵葉書にも共通するものです。
特に、「頭語」「時候の挨拶」「結びの挨拶」「結語」の選び方には細かなルールがあるため、
適切に使い分けることで、より印象の良い挨拶状になります。
意外と知らない挨拶状の豆知識
📌 「拝啓」のペアは「敬具」だけじゃない?
一般的に「拝啓」の結びは「敬具」とされますが、
実は送る相手や状況によって異なる表現を使うこともできます。
- 目上の方に送る場合:「拝啓」→「敬白」
- より丁寧な表現をしたい場合:「謹啓」→「謹言」
適切な組み合わせを選ぶことで、より洗練された印象を与えることができます✨
📌 挨拶状には「句読点」を使わないのが正式マナー
「、」や「。」を使わないのが、正式な手紙の作法とされています。
その理由は、句読点が使われ始めたころは、
子どもが文章を読みやすくするための補助的な役割を果たしていたため、
大人向けの正式な文書では不要とされていたためです。
また、句読点には文章を区切る役割がありますが、
「縁を切る」ことを連想させるため、挨拶状では避けるのが一般的です。
細部にこだわることで、より品格のある挨拶状になります。
挨拶状は、ビジネスの場での第一印象を決める大切なツールです。
ちょっとした工夫で、より丁寧で好感の持てる一通に仕上げることができます。
ぜひ、挨拶状を送る際の参考にしてみてくださいね!☺
弊社では、挨拶状の原稿の作成からサポートいたします。
まずは、お気軽にお問合せください✨
サンコー印刷では情報発信の様々なノウハウを活かし「伝わる」ホームページ制作も承っています。

